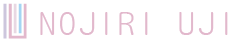葬儀の流れ
- ホーム >
- 葬儀の流れ
葬儀の基本的な流れ
1. 危篤
2. ご逝去(ご臨終)
3. 葬儀社手配
4. ご遺体搬送・安置
5. 葬儀のお打ち合わせ
6. 葬儀準備
7. 納棺・湯かんの儀
8. 通夜
通夜振る舞い
9. 葬儀・告別式
10. 火葬
11. 初七日法要
12. 精進落し
13. 散会・ご帰宅
事前準備
1.危篤 → 2.ご逝去(ご臨終) → 3.葬儀社手配 → 4.ご遺体搬送・安置 → 5.葬儀のお打合わせ → 6.葬儀準備
故人を悔いなく送るためには、葬儀の事前準備はとても大切です。慌ただしい中の準備となりますが、やるべきことをしっかりおさえ、わからないことは何でも葬儀社にお尋ねください。
1. 危篤
危篤連絡を受けても、慌てずに冷静になりましょう。まずは危篤者の身近な方々への連絡や、休みが必要な場合は職場への連絡が欠かせません。故人と親しい方や会って欲しい方への連絡は事前に「連絡リスト」を作っておくのもおすすめです。
2. ご逝去(ご臨終)
ご逝去(ご臨終)後は末期の水を取る、エンゼルケア、死亡診断書・死亡届の受け取り、臨終を知らせるべき関係者への連絡、病院への支払いといった対応が必要です。失意の中にあっても、遺族の方はこうした対応を行わなければいけません。
3. 葬儀社手配
故人のご遺体は病室から病院内の霊安室へと移されますが、霊安室には基本的に数時間ほどしか滞在できません。このタイミングで葬儀社(搬送先)の手配を行うのが一般的です。
4. ご遺体搬送・安置
葬儀までの間、ご遺体を安置しておく必要があります。病院の場合、ご逝去後はすぐに搬送を求められますので、早急に搬送先を決め、搬送業者の手配をする必要があります。一般的には手配した葬儀社が、ご自宅や葬儀会館・民間業者の安置所に寝台車で搬送します。
5. 葬儀のお打ち合わせ
葬儀の打合わせを進めるにあたり、喪主の決定は欠かせません。
葬儀社が決まり、ご遺体が安置されましたら、葬儀社の担当者と葬儀の打ち合わせに入ります。その後「一般葬か、家族葬か」など葬儀形態を決め、次に宗教の確認、場所と日程、葬儀プランなど、故人の遺言や遺族の意向をふまえて決めていきます。
6. 葬儀準備
葬儀前にやるべき準備として、打ち合わせと並行して死亡届の提出、遺影写真の準備、弔辞の依頼などがあります。喪主を中心に遺族・親族で協力して行いましょう。
葬儀までの運び
7.納棺・湯かんの儀 → 8.通夜 → 9.葬儀・告別式 → 10.火葬
7. 納棺・湯かんの儀
葬儀の前には、最後のお別れをするために、故人の身なりを整え、棺に納めてから送り出す「湯かんの儀」と納棺を行います。具体的にはお身体を清拭し、お化粧やお着替えを施しお棺にお納めします。
納棺の際には、副葬品も一緒に棺の中に入れていきます。副葬品として入れられないものもあるので、こちらは事前に確認しておきましょう。
8. 通夜
葬儀の1日目に行われる通夜は、多くの方が参列する儀式です。近年は、夕方6時から?7時ころから行われ、親族だけでなく縁のあった方々が集まり、故人を弔います。
参列しやすい時間帯であることから、葬儀・告別式よりも参列者が多くなることもあります。
通夜振る舞い
通夜振る舞いとは、通夜の後に設けられる食事会のことです。通夜振る舞いは単なる食事会ではなく、「喪家が弔問客に対して感謝の意を表す」「故人を偲ぶ」っという2つの意味があります
9. 葬儀・告別式
故人との最後のお別れをするのが葬儀・告別式です。
仏式の場合、読経の中で宗教者が引導を渡すことで故人は現世に別れを告げ、迷いなく仏様のもとへ導かれます(宗旨・宗派により異なります)。参列者は焼香と合掌を行い、故人との最後の別れをします。
これらも、宗派により、お別れの仕方、考え方、作法は変わります。
10. 火葬
故人と最後のお別れをして出棺したあとは、火葬場へと移動します。そして炉の前で「納めの儀」を行い、棺を火葬炉に納めます。火葬後は、遺骨を骨壷に入れる「拾骨」を行います。
火葬にあたっては「火葬許可証」が必要になります。慌ただしい中で、この火葬許可証を当日に忘れてしまうこともあるため、葬儀社に預けておくことをおすすめします。
葬儀後
11.初七日法要 → 12.精進落し → 13.散会・ご帰宅
葬儀後は初七日法要・精進落しを行い散会となります。初七日法要を当日に行うことが増えてきていますが、地域によって異なります。初七日法要をいつ行うかで葬儀後の対応も変わってきますので、事前に葬儀社へ確認しておきましょう。
11.初七日法要
初七日法要とは、故人の命日から数えて7日目に行う法要ですが、近年では葬儀と同じ日に初七日法要を行うことが増えています。この法要では故人が極楽に行けるよう、読経し成仏を願います。
12.精進落し
初七日法要のあとは、精進落しです。葬儀でお世話になった参列者をもてなします。遺族は下座に座り、最上座には宗教者に座っていただきます。宗教者が参加できない場合は、お布施として御膳料をお包みする事が多いです。
13.散会・ご帰宅
精進落しをもって、葬儀は散会となります。喪主は最後に散会の挨拶をし、宗教者や参列者に感謝の気持ちを述べましょう。
葬儀後も、やらなくてはいけない手配は残っています。事前に確認し、見落としのないよう気をつけましょう。